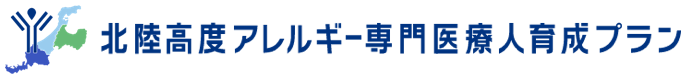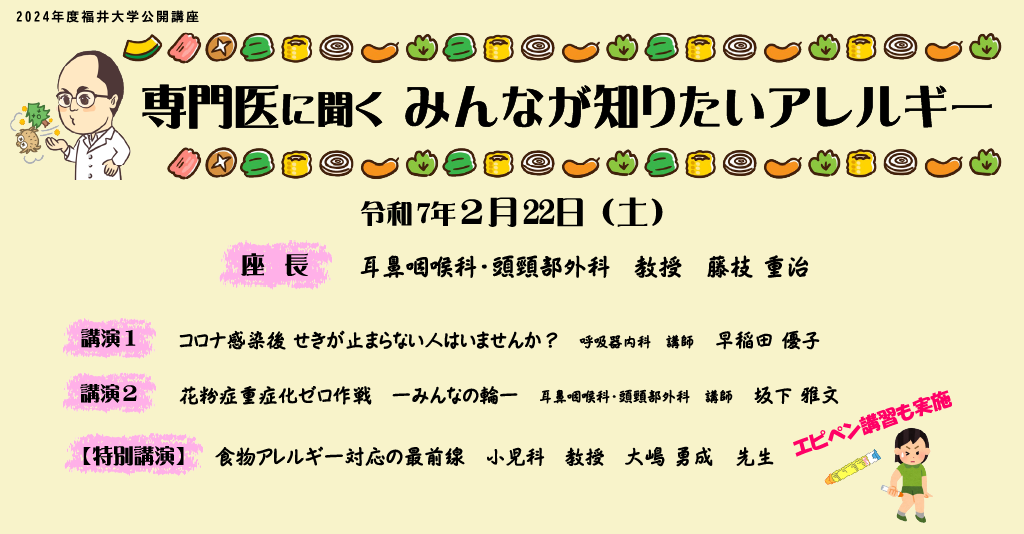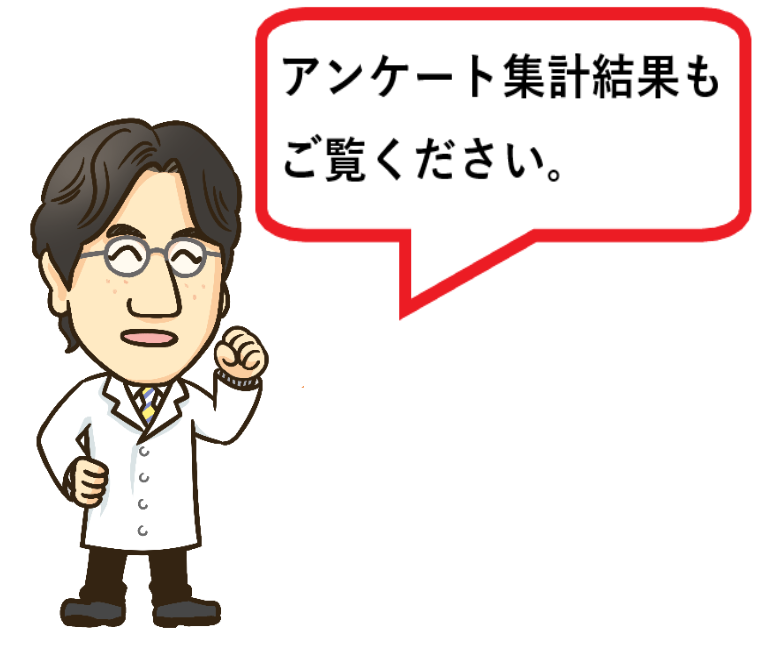専門医に聞くみんなが知りたいアレルギー
Q&A
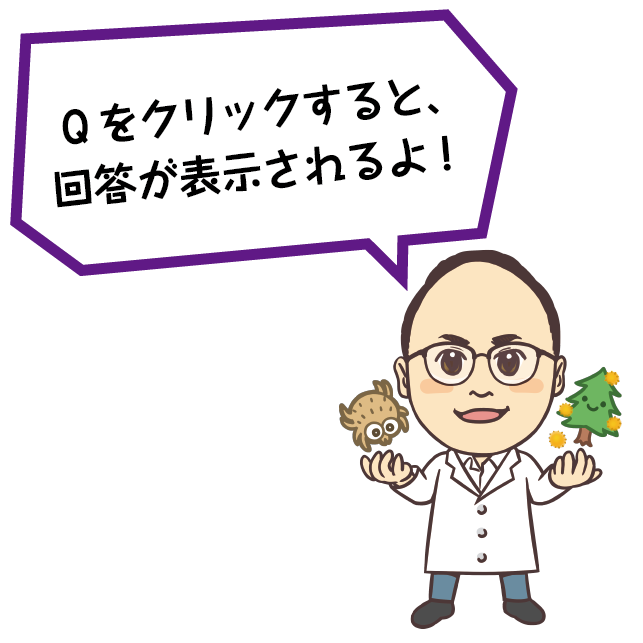
1.コロナ感染後せきが止まらない人はいませんか?(早稲田先生)
Q1コロナ感染後の長引く咳は、アレルギーによる咳とメカニズムが同じなのでしょうか。
全てがそうではないですが、いわゆる感染後に悪くなるアレルギー性の咳(咳喘息やアトピー咳嗽)のことも多いと思います
Q2コロナ感染後の長引く咳で受診した場合、どんな薬が処方されるのか?順番に(段階的に)もう一度教えて下さい。
医師によって異なるとは思うのであくまで私の例ですが、β2刺激薬内服(気管支拡張薬)をしばらく使って効果があれば咳喘息と考えて吸入ステロイド/長時間作用型β2刺激薬を、β2刺激薬内服で効果がなければ、抗ヒスタミン薬を使うことが多いです
2.花粉症重症化ゼロ作戦 -みんなの輪-(坂下先生)
Q1花粉症の薬は子どもにも使えるものもたくさんあるのでしょうか。
はい、子供用の容量もあります。お勧めしている第2世代抗ヒスタミン薬や点鼻ステロイドなどにも子供用のものは多数あります。
Q2子どもの抗ヒスタミン薬は眠くならないのでしょうか?
はい、眠くなりにくい抗ヒスタミン薬はあります。現在、全国的にお進めされているのは第2世代抗ヒスタミン薬ですので、医療機関などでも、「眠くなりにくい第二世代抗ヒスタミン薬がほしい」といっていただくとより良いと思います。
Q3インナーマスクは効果的ということですが、販売されているのでしょうか?
インナーマスクは、販売はされていないため、ご自身で組み合わせて作ってもらうのがよいと思います。
Q4花粉症対策として、薬の処方がすすめられているが、スギやヒノキなどの間伐を積極的にすすめるのがすじであると思う。何故、推進されないのか?花粉の出ないスギの開発が進められているが、おかしいと思う。
おっしゃる通りです。木材の積極的利用は、林野庁、環境省が中心になって、発生源対策として進められています。
(政府の花粉症対策3本柱 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kafun/dai4/sankou.pdf)
昔は森林の管理が行き届いており、間伐、枝打ちがしっかりなされていたと聞きます。そのため、子供達は学校の後に、林の中を遊びまわるスペースと明るさがあったと聞きます。今では林はうっそうしており、そのような姿はありません。さらには、建材としてのスギの利用が十分にあり、循環社会があったのですが、戦後は外国からの安い木材の輸入により国内産の木材が利用されなくなったことが大きな原因とされています。
3.(特別講演)食物アレルギー対応の最前線(大嶋先生)
Q1アレルギー報告のない学級は5時間目に体育が入っていることがあります。アレルギー報告がない学級でも午後の体育はやはり避けたほうがいいのでしょうか。
5時間目に体育を避けて時間割を組むことが可能であれば対応してもよいですが、避けることは必ずしも必要ではないでしょう
Q2暑い時期に校外学習で外に出ているときにアナフィラキシーのような症状が出たとします。お姫様抱っこのような横抱きで涼しい場所に移動させるのはいいでしょうか。
横抱きで移動されるのは良いでしょう。この際、足の方の血液が少しでも頭の方に行きやすいよう、足が心臓の位置より下になりすぎないように、頭が上になりすぎないようにしましょう
Q3交差反応で出る口腔内の炎症はどのように治療するのでしょうか。
口腔内に残っているアレルゲンを少しでも減らすため、うがいをして外に出してしまいましょう。その後で、抗ヒスタミン剤があれば内服します
Q4エピペンを使用してよいか迷うときがあると思いますが、もし結果的に必要ない場合に打ってしまったとしても問題ないのでしょうか。
アナフィラキシーでないのにエピペンを打っても、しばらく動悸を感じるかもしれませんが、数分間すれば薬の効果がなくなるので大丈夫です。持ち方の上下を間違えて、自分の指に打ってしまうことが稀に報告されていますが、しばらく指先が真っ白になりますが、数分たてばもとにもどります
Q5エピペンに関して、筋肉内注射ですが、なぜ臀筋や三角筋ではなく、大腿前部外側に打つのでしょうか?
エピペンを打つと先端から長い針が出ます。この針が筋肉の奥にある骨や神経、血管に当たらないよう、筋肉の分厚い部分で、神経や太い血管がない大腿前部外側が打つのに適した場所となります
Q6アナフィラキシーは、クルミ・ナッツ類による原因が増えているとのことだが、消費量が増えているのか?
クルミ、ナッツ類の輸入量が増加していることから、消費量も増加していると考えられます
Q7食物アレルギーを防ぐために、子どもにナッツ類を早く食べさせるとよいのか?
ピーナッツアレルギーの多い国では、ピーナッツ製品を早期にたべさせるとピーナッツアレルギーの発症が抑制されることが報告されています。ただし、ピーナッツアレルギーの少ない国でも発症が抑制されるかはまだ証拠が不十分です。ナッツ類を早く食べさせるとナッツ類アレルギーが抑制できるか否かの証拠は現段階ではありません
Q8最近増えていると言われるクルミアレルギーの割合は?
即時型アレルギーの原因食物の約15%を占めています